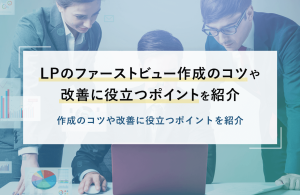【例文あり】ランディングページのキャッチコピー作成で押さえるべきポイントと注意点を解説

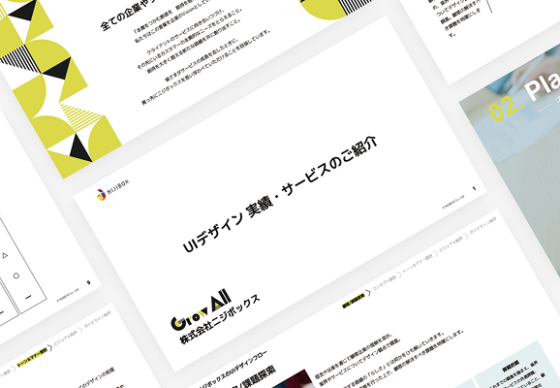
リクルートや大手企業の実績多数!
ニジボックスのUIデザインフローや
案件事例をご紹介!
広告や検索エンジンから流入するランディングページは、ユーザーの意欲を刺激し、商品・サービスの購入を後押しします。そのため、最後までランディングページを読んでもらえるよう、ユーザーの心をつかむキャッチコピーを作成しなければなりません。
この記事では、ランディングページでのキャッチコピーの役割や、効果的なキャッチコピーの作り方を解説します。
目次
ランディングページにおけるキャッチコピーの役割

ランディングページのファーストビューに表示されることの多いキャッチコピーは、訪れたユーザーが最初に目にする部分であり、ページのつかみに該当します。
つまり、キャッチコピーへの共感が、ランディングページを読み進めるきっかけになるのです。
それでは、ランディングページにおけるキャッチコピーの役割を詳しく解説します。
ランディングページ(LP)とは?
ランディングページ(LP)とは、商品やサービスの訴求をし、購入や資料請求などを促すことを目的としたページのことです。
広告や検索流入で興味を持ったユーザーが、商品・サービスの購入といった具体的な行動を起こすように促す役割があります。
また、打ち出す広告の表現内容と、ランディングページの訴求内容をリンクさせることで、訴求力を高めることが可能です。
例えば、英語教材を販売する場合、ビジネスマン向けの広告から移動するなら、ランディングページでもキャリアアップや転職に有利なことを記載します。
すると、教材を使用した後の姿をイメージしやすくなり、ユーザーの購入意欲は高まります。
ランディングページについては以下の記事でも詳しく解説しています。
■関連記事:
【初心者向け】ランディングページ(LP)とは?作り方やポイントも丁寧に解説!
ランディングページの要素とキャッチコピーの重要性
ランディングページは、「ファーストビュー」「ボディ」「クロージング」という3つの要素で構成されています。各要素の役割は、以下の通りです。
- ファーストビュー:最初にユーザーの目に入る部分。ユーザーは最後までランディングページを読むかをここで判断する
- ボディ:商品・サービスの紹介を通して、ユーザーの購入意欲を高める部分
- クロージング:ユーザーが購入や資料請求の申し込みを行う部分
ランディングページのキャッチコピーは、ファーストビューに該当します。
キャッチコピーは、ボディを読むかどうか判断する要素の一つで、キャッチコピーがユーザーに刺さらないと、ユーザーはすぐにページを離脱してしまうでしょう。
つまり、キャッチコピーは特に重要な役割を担っているといえます。
ランディングページのファーストビューについては以下の記事でも詳しく解説しています。
■関連記事:
ランディングページ(LP)のファーストビュー作成のコツや改善に役立つポイントを紹介
キャッチコピー作成のポイント3点

ユーザーの興味や意欲を引くキャッチコピーは、商品・サービスをまとめただけでは作成できません。
ここでは、質の高いキャッチコピーの作るための3つのポイントを紹介します。
ランディングページの離脱率を下げるために、効果の高いキャッチコピーの作り方を身につけましょう。
1.ターゲットを決めておく
キャッチコピーを作る前には、売り込みたい商品・サービスのターゲットを明確にしておきましょう。ターゲットを明確にすることで、どのような売り方・伝え方が良いのかを検討しやすくなります。
また、ターゲットを決める際には、具体的な人物像を作り上げるほど訴求力のあるキャッチコピーを作りやすくなります。
つまり、キャッチコピー作成においては、より詳細な人物像となる「ペルソナ」作成が重要といえるでしょう。
ペルソナの特徴や作り方、メリットなどは、下記の記事で詳しく解説しています。
ユーザー心理に一致するキャッチコピーを作るために、記事の内容を参考にしてペルソナ作成に取り組んでみてください。
■関連記事:
「ペルソナ」とは?ターゲットとの違いやペルソナ設定の重要性までやさしく解説
2.メッセージは簡潔かつ明確に
商品・サービスをアピールするために、思わず特徴やメリットなどをたくさん伝えたくなるでしょう。
しかし、キャッチコピーの文字数が多いと1番の魅力がユーザーに伝わりづらい上に、ユーザーがページを離れるきっかけにもなりかねません。
ランディングページで、ファーストビューからボディへ読み進めようと判断する時間は数秒です。
時間をかけて、ファーストビューを読むユーザーはいないため、キャッチコピーではシンプルかつ明確な内容にする必要があります。
一目で魅力が伝わらないキャッチコピーでは、商品・サービスの売上アップは期待できません。
3.流入元に合わせて変化させる
ランディングページを作る際は、流入経路(広告・検索流入など)に合わせてランディングページを複数作成し、それぞれに合わせたキャッチコピーを作りましょう。
1つのキャッチコピーを複数の流入経路で使いまわすと、流入元のページを訪れたユーザーの属性と合わなくなります。
その結果、自分向けの商品・サービスではないと判断され、ランディングページの離脱率が高まります。
多くの場所に広告を出す場合には、出稿場所に合わせたキャッチコピーを1つずつ作成しましょう。
ランディングページで使える効果的なキャッチコピー例8選
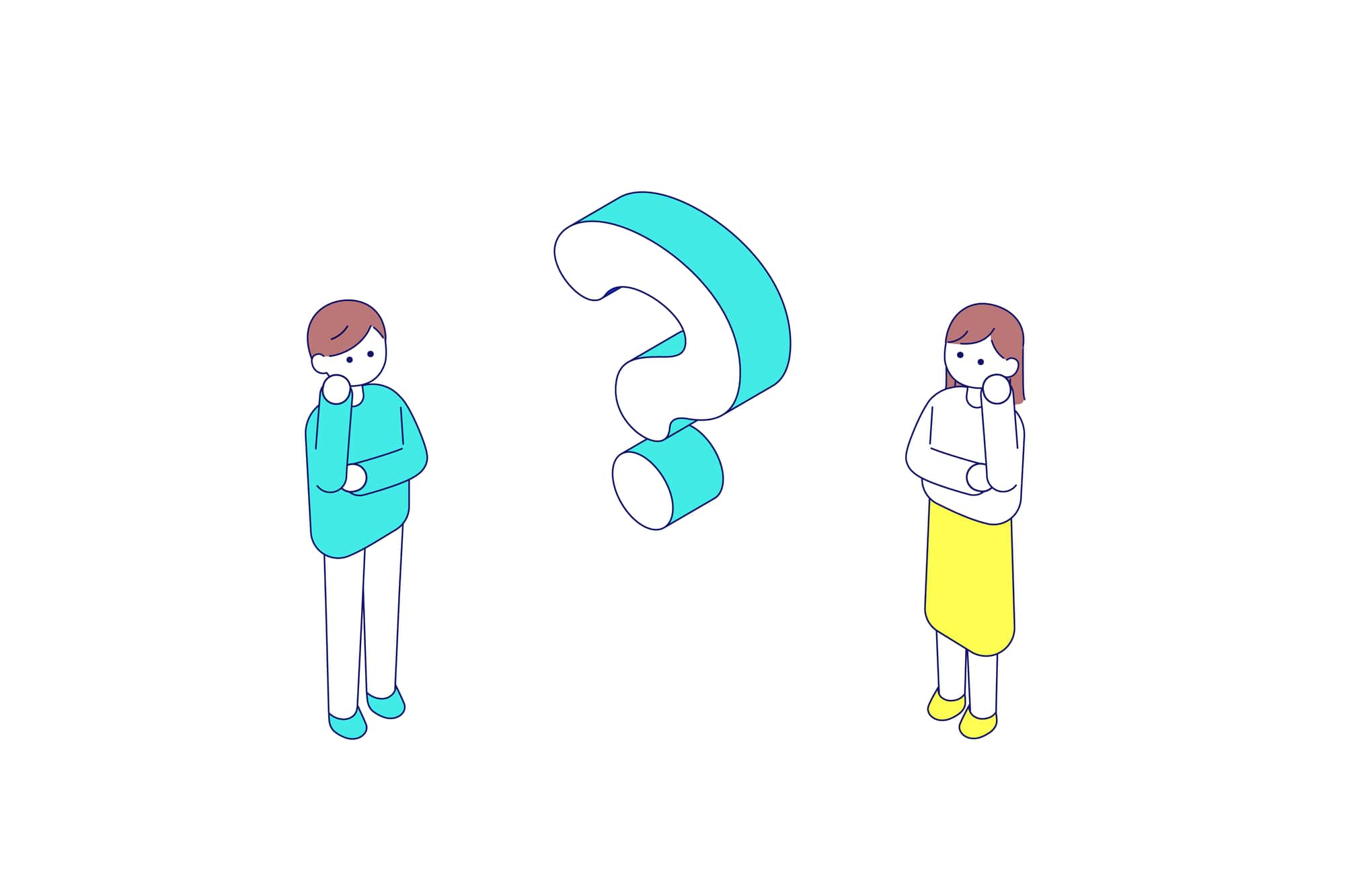
キャッチコピーの作成では、短い文章で簡潔に魅力を伝えることが大切です。
ここでは、キャッチコピー作成で使えるテクニックを、例文とともに解説します。キャッチコピー作成で悩んだり行き詰まったりした場合は、ここで取り上げた表現を元にキャッチコピーを作成してみましょう。
1.具体的な数字を提示する
一目で商品・サービスの魅力を表現するためには、具体的な数字を提示することが有効です。数字が加わることで説得力が増し、ユーザーが商品・サービスを使うメリットをイメージしやすくなります。
また、数字で表現する際に「約70%」のように表現すると、ユーザーは70%なのか69%なのか判断できません。「約」などの表現を用いて切りのいい数字にするのではなく、正確な数値を使うことで、リアリティが生まれます。
【例】
- 天然素材だけを使用した→「100%天然素材の○○」
- 多くの人がリピート→「リピート率87%」
2.意外性を重視する
ユーザーがランディングページを読みたいと思うのは、他の商品・サービスとは違う点があり、特徴や魅力を詳しく知りたいと思うからです。
似たようなキャッチコピーでは読まなくてもよいと判断され、ファーストビューで離脱される原因となります。
つまり、キャッチコピーには、意外性を重視した内容を加えて興味を引くのが有効です。
意外性を加える表現では、「常識をくつがえす」「難しいことが簡単になる」といった要素を組み込むとよいでしょう。
こうした表現は、新しい方法を試したい欲求を刺激し、「成功するかもしれない」と思わせられます。
【例】
- 1日1回の○○はもう古い!
- 学年最下位から3ヵ月で学年トップになった勉強方法
3.権威性を持たせる
企業が商品・サービスを売る際には、わざわざデメリットを伝えません。
ランディングページにも、他社の商品・サービスより優れている点だけが多く書かれています。
しかしその場合、本当に書かれている効果があるのか、ユーザーに怪しまれることになりかねません。
このようなユーザー心理を変えるために有効なのが、キャッチコピーに権威性を持たせることです。権威性を持たせることで、ユーザーからの商品やサービスへの信頼度が高まります。
第三者がおすすめしていることをキャッチコピーに加えれば、権威性を持たせられます。
例えば「芸能人が愛用している」「テレビで取り上げられた」などの表現をプラスすると、商品・サービスへの信頼度が高まるでしょう。
【例】
- 大手メディア掲載後に即完売した○○!
- 医師が監修のもと開発した○○
4.ユーザーが気づいていない課題にアプローチする
「この商品・サービスを使わないと損をする」という表現も、ユーザーの購買意欲の向上には効果的です。
特に、ユーザーが抱えている課題にアプローチをする商品・サービスの購入は、メリットを得るための購入よりも実行性が高いといわれています。
しかし、そのためにはまずユーザー自身に「自分が気づいていない課題」に気づいてもらうことが必要です。
【例】
- 78%の人は間違えている?○○の方法・毎日○○するのは今日で終わりにしませんか?
ただし、必要以上に不安をあおるような表現は逆にユーザーの離脱を招くため注意しましょう。
また、数字を使って具体性を持たせたりすることも、ユーザーの気づいていない課題にアプローチをする面で効果的です。
具体的な表現になるほど、ユーザーが抱える課題のイメージもリアルになるからです。他の方法をうまく組み合わせて、ユーザーに利用しないと困ることを伝えましょう。
5.ベネフィットを伝える
ベネフィットとは、「利益」や「恩恵」を指す言葉です。似た言葉にメリットがありますが、以下のような違いがあります。
ベネフィット:商品・サービスを利用することでユーザーが得られる利益・恩恵
メリット:商品やサービスそのものの特徴や利点
ユーザーが商品・サービスの利用を決めるのは、利用することでベネフィット(利益や恩恵)が得られると確信した場合です。
そのため、キャッチコピーを作る上では、商品・サービスを使った場合のベネフィットを提示することを意識しましょう。
具体的には、ユーザーが抱えている悩みや課題に沿ったベネフィットを伝えます。「なぜ自分が抱える問題が解決するのだろう」という興味から、ランディングページを最後まで読んでもらいやすくなるためです。
【例】
- 身体の不調を整え活力のある毎日へ!
- 転職市場で有利になり、今よりも年収アップ!
最初に作成したターゲットやペルソナから抱える悩みを想定して、ユーザー目線のベネフィットを盛り込んだキャッチコピーにしましょう。
6.好奇心をくすぐる
キャッチコピー作成において活用できる心理的な現象に、「カリギュラ効果」が挙げられます。カリギュラ効果とは、「禁止されたことほどやりたくなる」という心理を表したものです。
つまり、見てはダメと言われたら見たくなる行動などは、カリギュラ効果に該当します。
キャッチコピーでカリギュラ効果を活用するには、「見ないでください」「スクロールしないでください」という表現を使います。
「○○な人は見ないでください」という表現にすることで、条件に該当する人ほど見たくなるように誘導します。
【例】
- 今の給料に満足している人は見ないでください
- 痩せたくない人は絶対にスクロールしないでください
7.「自分のこと」だと思わせる
商品・サービスのメリットやベネフィットの対象が自分だと思わせることも、キャッチコピー作成では重要なポイントです。そこで有効なのが、心理学の「カクテルパーティー効果」です。
カクテルパーティー効果とは、多くの情報がある中でも、自分に関連した情報は自然と入ってくることを指します。作成したターゲットやペルソナに合わせた表現を取り入れて、キャッチコピーを作成しましょう。
例えば、女性をターゲットにする場合は、単に「女性へ」と表現するよりも「30代女性へ」と表すほうが自分のことだと思われやすくなります。
さらに、「肌のくすみが気になる30代女性へ」など、具体的な表現が加わるほど興味を引くことができるのです。ターゲットやペルソナの設定を細かく決めるほど、カクテルパーティー効果を生かしやすくなります。
【例】
- そろそろ転職を考えている社会人へ
- 肌のくすみが気になる30代女性へ
8.購入の不安や手間を解消する
魅力的な商品・サービスでも、実際に使ってみるまでは効果があるか分からないものです。
さらに、ユーザーには後悔することを避けたい気持ちがあるため、効果がなかったときのことを考えて、購入を控えることも少なくありません。
そういった状態を避けるために、購入時の不安を解消する内容を、キャッチコピーに取り入れてみましょう。
【例】
- 無期限保証でいつでも対応!
- 30日間全額返金保証
キャッチコピー作成時の注意点

インパクトの強いキャッチコピーはユーザーの心に刺さりやすいことから、表現や言葉のインパクトを重視した結果、過激な内容になることがあります。
過激なキャッチコピーは、大きなトラブルを引き起こす原因にもなりかねないため、注意しましょう。
ここでは、キャッチコピー作成時の3つの注意点を解説します。
1.ネガティブな表現を使いすぎない
ユーザーの興味を引くために、強く不安をあおるような過剰な表現を用いると、自社の商品・サービスへも悪い印象を与えてしまいます。そのため、ネガティブな表現を使いすぎないよう、注意してキャッチコピーを作成しましょう。
例えば、「○○では絶対に失敗する!」のようなキャッチコピーでは、本当にこの商品・サービスなら成功するのかと、ユーザーの懐疑心をあおる可能性があります。
キャッチコピーが強すぎると、ユーザーの期待値が過剰に上がる可能性があるため、結果的に紹介する商品・サービスのハードルが高くなり、ランディングページの効果も薄くなります。
また、自社の商品やサービスを利用してほしいからと言って、競合や従来の商品のネガティブキャンペーンをすることは厳禁です。
2.景品表示法や薬機法などの法律に注意
ユーザー心理として、「70%の人が効果を実感」と書かれた商品よりも、「絶対に痩せる」と書かれた商品のほうが魅力を感じます。
だからといって、実際の効果以上にアピールすることは、ユーザーをだますことにつながります。
このような実態と齟齬のあるキャッチコピーは、その商品やサービスに携わる人に不利益を与えてしまう可能性があります。
また、こうしたユーザーの不利益が起こらないよう、景品表示法や薬機法といった広告内容を規制する法律が制定されています。商品・サービスを良く見せようと、根拠のない情報やデータ以上の効果を記載すると、これらの法律に抵触し罰則の対象になることがあるため、注意しましょう。
キャッチコピーを作成する際は、事実の範囲内でユーザーの興味を引く内容にすることが重要です。ただし、正確なデータの範囲内でも、広告として使えない表現や言葉もあります。
表現の事前・事後チェックを徹底し、問題のないキャッチコピーを作成しましょう。
3.効果を必ず検証する
ランディングページのキャッチコピーを作成する目的は、商品・サービスの売上を向上させるためです。試行錯誤の中で生まれたキャッチコピーでも、実際に売上アップにつながらなければ、目的達成とはいえません。
そのため、作成したキャッチコピーがどのような効果をもたらしているのかを、検証することが大切です。
キャッチコピーの効果を検証する際には、ABテストが効果的です。ABテストとは、複数のパターンをユーザーに表示させて、パターンごとの成果を比較する方法です。
例えば、特定の流入経路で表示させるランディングページで、キャッチコピーの種類を複数用意してランダムに表示させます。
キャッチコピーごとの成約数を比較することで、ユーザーに刺さる表現を見つけられるのです。
そして、ABテストの結果を基にキャッチコピーを変更したら、変更前の流入量やクリック率からどのように変化したかを比較しましょう。
ユーザーアンケートを行い、決め手になった文章や表現を教えてもらうのも効果的です。
キャッチコピーは、一度作成したら終わりではありません。キャッチコピーの効果を検証して改善をし続けて、商品・サービスの売上アップを目指しましょう。
効果検証に使われるABテストについては以下の記事で詳しく解説しています。
■関連記事:
ABテストとは?サイト最適化に重要なテストを分かりやすく解説!実施の際の注意点も紹介
まとめ
ファーストビューに表示されるランディングページのキャッチコピーは、ユーザーが最初に目にする文章です。キャッチコピーでユーザーの心をつかめないと、それ以上ページを読む必要がないと判断されてしまいます。つまり、キャッチコピーの質は、商品・サービスの売上にも大きな影響を与えます。
ただし、効果を狙いすぎて過激な表現や根拠のない情報を記載したキャッチコピーにすると、ユーザーをだますことにつながるため厳禁です。
キャッチコピーを作る際は、紹介する商品・サービスの事実の範囲内で、的確にアピールすることが大切です。作成後は効果を検証しながら、ユーザーに刺さる誠実なキャッチコピーへと仕上げましょう。
下記資料では、人間中心設計の考え方をベースとしたUXリサーチ結果に基づいた、ニジボックスのユーザー課題解決型のUIデザインフローや、支援事例を一部紹介しています。
ご興味を持たれた方はぜひ、下記ダウンロードリンクよりご参照ください!
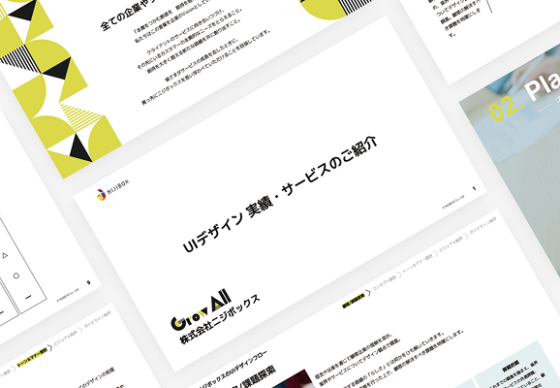
リクルートや大手企業の実績多数!
ニジボックスのUIデザインフローや
案件事例をご紹介!
監修者

丸山 潤
コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。