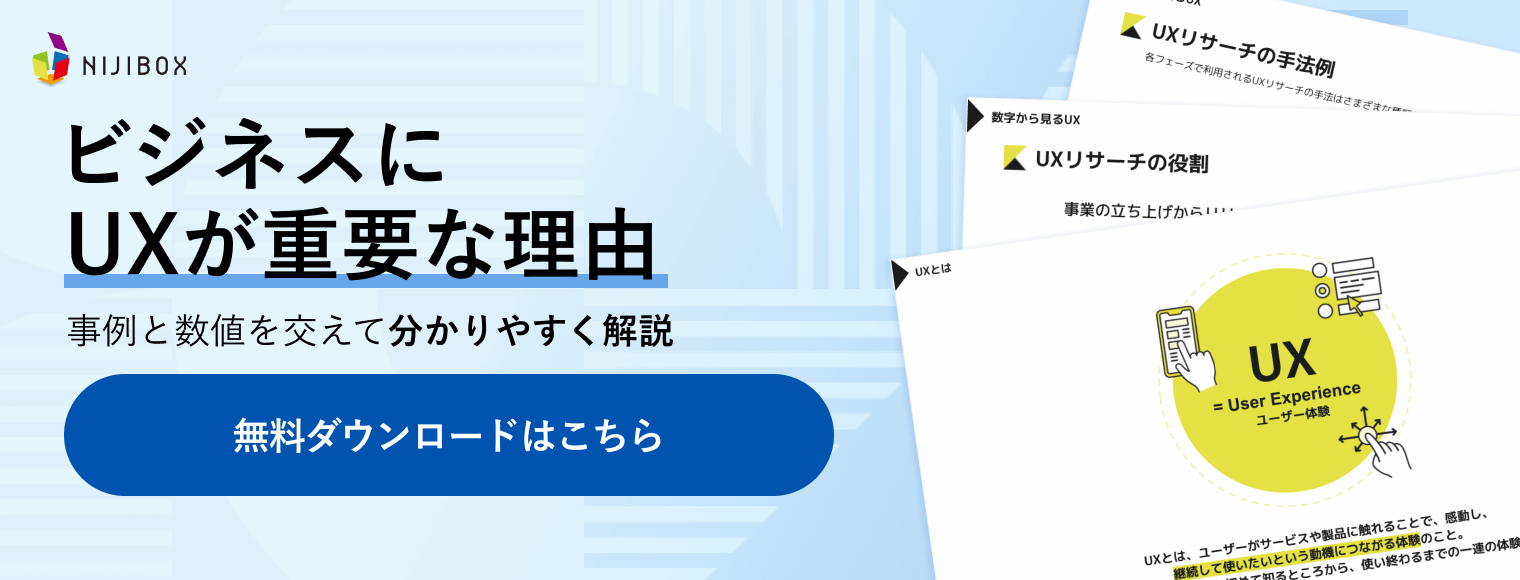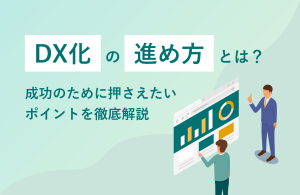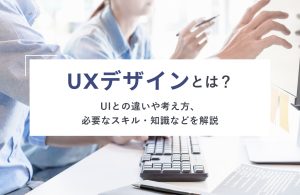DXとUXの関係性は?UXを意識してDXを進めるためのポイント
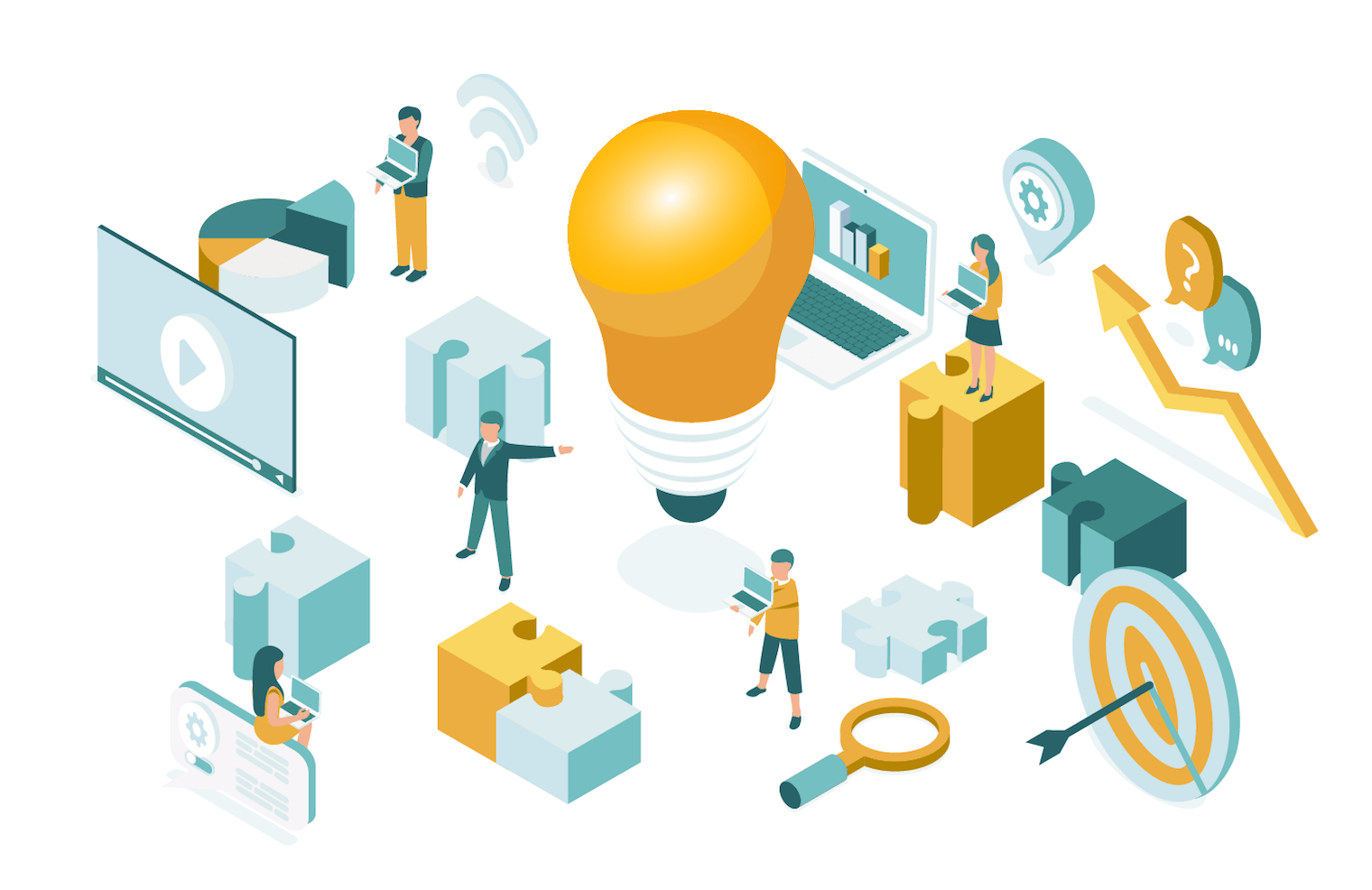
ニジボックスの案件事例をご紹介!
昨今、メディアでも耳にする機会が多くなったDX(デジタルトランスフォーメーション)。DXに関わるレポートとして経済産業省が発表した「2025年の崖」も、話題となりました。
一方では、UX向上させることが事業の成長に必要という声も多く聞こえてきます。UX向上のためには、DXが重要なポイントともなっているのです。
この記事では、DXやUXの基本情報とともに、DXとUXの関係性やポイントを解説していきます。
DXについては下記の記事で詳しく紹介しているので、こちらも参考にしてください。
■関連記事:
目次
DXとは
DXとは、「新しいデジタルテクノロジーを導入・利用することで、新しい価値を生み出し、ビジネスを変革し、その優位性によって事業成長させること」です。
まずは、DXの定義やなぜDXが推進されているかを見ていきましょう。
DXとは?まず定義を確認しよう
「デジタルテクノロジーによって、人々の生活にあらゆる面で良い影響を与える」
-エリック・ストルターマン
これが、2004年、最初にDXに対して定義をした言葉と言われています。
しかし、これはあくまで研究・学問上の定義です。
一方、ビジネス上の定義も、さまざまな企業が行っています。
例えば調査会社「IDC Japan」はDXを以下のように定義しています。
「企業が第3のプラットフォーム(※)技術を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデル、新しい関係を通じて価値を創出し、競争上の優位性を確立すること」
-IDC Japan
(※)第3のプラットフォーム=クラウド・ビッグデータ/アナリティクス・ソーシャル技術・モビリティーなど
この定義は、経済産業省のDXレポートにも引用されている定義です。
他企業の定義を見ても、多少の差こそあれDXを構成する「要素」は同じであることが多いです。
その要素とは、
- 新しい技術
- 新しい価値創出
- 競争上の優位性
の3つであるといえます。
DX推進の背景とは?「デジタル環境の進化」によるDXの加速
定義とともに理解しておきたいのが、今現在DXが叫ばれている背景です。
DX推進の背景とは、一言にまとめると「デジタル環境の進化」です。
エリック・ストルターマンの定義を思い出してください。
「生活のあらゆる面」という言葉がありました。
人々が「あらゆる面」でデジタルと接続できる環境が、DXには不可欠なのです。
誤解を恐れずによりかみ砕いて言うと、スマートフォンをはじめとしたさまざまなデバイスが私たちの生活のあらゆる面に浸透しているので、ネットワークを通してデジタルサービスと「いつでも」、「どこでも」接続可能な環境が整ったことが、DXを加速させています。
5Gによって、よりリアルタイム性の高いサービスが生まれるなど、今後は今まで以上に加速度的に技術が進化していくでしょう。
技術が進化すれば、より新しい価値を生みやすくなります。
つまり、この事実は、DXに取り組まないとこの環境に適応したビジネスを展開できず事業成長のスピードが遅れたり、市場競争に敗北したりする未来を示唆しています。
UXとは
UXとは「製品やサービス、システムなどの利用を通じてユーザーが得られる体験の全て」を表します。
商品やサービスの機能はもちろんですが、見聞きする他のユーザーの感想や利用している時に起こったことなどもUXの一部とされています。
UXについては、下記で詳しく解説しているので合わせて参考にしてください。
UXデザインとは
上述したUXをより良くするために設計することが、UXデザインです。
UXはユーザーの体験のため、商品やサービスの提供者側がコントロールすることはできません。しかし、より良いUXを生み出すための工夫はできます。UIやサービス自体の磨き込みを含めて、UXをより良くするための設計がUXデザインです。
近年、どんな商品・サービスにおいてもモノだけではなく、体験や精神的な満足感を重視して消費行動が行われるようになってきました。そのため、競合に勝つためにも、UXデザインがより重要になっています。
また、UXは顧客だけではなく、業務における従業員に対しても考慮すべきです。業務をスムーズに進めるためには、従業員(=ユーザー)がいかに業務をすすめやすいか設計することが重要だからです。
DXのカギとなるのは「UXデザイン」と「事業価値」
ここからは、DX化を成功させるためにカギとなる2つのポイント、「UXデザイン」と「事業価値」について解説します。
DX成功のためにはUXデザインが重要
DX推進の際には、UX=利用者のユーザー体験を考えることが非常に重要です。
たとえば、社内の既存業務をデジタル完結するシステムを構築するプロジェクトの場合、そのシステムを最終的に使用するのは従業員です。
従業員の業務実態に即したシステム設計・UI設計を行うことで初めて業務負荷が軽くなり、使いやすいシステムになります。
そうでなければ、デジタル化したところで業務効率の改善に繋がらず、コスト削減にも繋がりません。
つまり、従業員=ユーザーの声を聞かずに形だけのデジタル化を行っても、DXは成功しないということです。
また、商品・サービスの提供機会におけるDXを考える際には、UX=お客様のユーザー体験を考えることが重要となります。
よって、社内業務の改善であれば従業員の声を、市場向けの新サービス開発であれば顧客の声を聞きながら、DXを推進することが重要です。
事業価値の本質に立ち返ることで、強いエンゲージメントが可能に
UXデザインと同じくらい、DX化において重要なのが「事業価値の本質」です。
例えば、飲食店の事業価値とは何でしょうか?
ここですぐに答えを出した人は、もしかすると事業価値の本質を理解していないかもしれません。
なぜなら、飲食店という大きなくくりでは、共通の事業価値を見出すのが困難だからです。
星を獲得するような高級レストランと、ファーストフード店ではその事業価値は異なります。
前者は、美食と非日常の空間、優れたサービスで「特別な日」を提供することが事業価値といえます。
後者であれば、時間とお金をかけずに一定水準の食事をいつでも提供できること、でしょう。
もっと言うと、同じファーストフードでも、店によってその事業価値は異なるかもしれません。
つまり、事業者の数だけ事業価値があるのです。
だからこそ、一度「私たちは、どんな価値を提供しているのか?」に立ち返りましょう。
飲食店であれば、「単に食事を提供すること」ではなく、それを通してどんな価値を生んでいるのかを考えましょう。
その価値を無視して闇雲にデジタル化を推進しても、おそらくユーザーにとって的外れな施策となってしまいます。
よって、事業価値の本質を改めて捉え、あるいは再定義して、いかにデジタルで優れた顧客体験を届けるかを考えること。
これを徹底的に突き詰めることが、DX推進においては重要なのです。
「DX=手段」を常に念頭に
企業がDXに取り組む際にまず一番に気をつけなければならないのが、DX化自体を目的としてしまうことです。
「最近よく聞く言葉だし、やらないといけないんだよね……?」
といった認識だけで始めてしまうと、ただなんとなくツールだけ導入してみたけど全く成果につながらなかったり、業務フローに適していなかったりといったような、ただコストだけが増える最悪の展開になってしまいがちです。
また、例えば紙ベースのものをPDF化して「とりあえずデジタル化してみました」で満足してしまう状態になるのも避けなければなりません。なぜなら、それは「デジタル化」であり、デジタルにすることが目的だからです。
DXとはこの「デジタル化」とは似て非なるものです。
DXはあくまで手段であるため、デジタル変革により、既存業務の改善をしてコスト削減につなげたり、新しい価値を生むことで事業成長につなげることが大切です。
これをまず理解した上で、次項以降の成功法則や実践方法を見ていきましょう。
UX向上のためのDXを進めるポイント
UX向上を目的としてDXを進めていくためには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
ここでは、UX向上のためのDXを進める上でのポイントを解説していきます。
ユーザーデータを活用する
UXを向上させるためには、まずはユーザーのことを知ることが重要です。
- 何に困っているのか
- どんなニーズがあるのか
- 何を比較したいのか
- 何ができれば便利なのか
など、商品・サービス自体だけなく、購入プロセス全体におけるユーザーの評価や感じている事などを分析していきましょう。
ユーザーデータを収集する手段としては、アンケートやユーザーインタビューが有効です。ユーザーの声を元に、DXで何を優先すべきなのかを検討していくとよいでしょう。
社内業務におけるDXでも、従業員へのアンケートやインタビューを通して、施策を検討していくことが重要です。
アンケートやインタビューについて詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
一部門ではなく、全社で取り組む
DXの実務を担うのが、情報システム部門や総務部門だったとしても、DXについての理解は全社的に浸透していることが非常に重要です。
DXの推進過程においては、導入したシステムへの理解など従業員の負担が一時的に増え反発が生じることも少なくありません。
しかし、最終的には従業員の業務負担軽減や顧客満足度の向上による売り上げアップなど、会社全体にとって必要なことです。そのため、DXの意義やゴールの共有など、全社でDXに取り組む意識を持ってもらうための工夫が必要となります。
継続的にDXを推進する
DXは、「一つのツールを導入して、一つのプロセスをデジタル化して終わり」というものではありません。継続的に、DXを進めて業務効率化や顧客満足度の向上を目指していきましょう。
そのためには、PDCAを回すことも重要です。すべてのDX施策が上手くいくとは限りませんし、たとえ最初は成果が出ても、周辺環境の変化などによって状況が変わることもあります。実施した施策については、きちんと評価をし、次の改善につなげていくことが重要です。
DX・UXの専門人材を採用する
DXやUX向上に関しては、比較的新しい考え方ということもあり、全スタッフが精通しているわけではありません。
特に、DXはITに関しての専門知識も必要なため、経験や知識のある専門人材を採用することも施策として重要です。ただし、ITスキルがあっても、経営・事業・組織の課題把握がきちんとできていなければ、DXは上手く推進されされないため、課題把握やプロジェクト推進もできる人材が必要です。
人材の採用あるいは、既存社員を育成するという方法の他に、外部の専門組織に委託するという方法もあります。外部組織であれば、経験やノウハウを持った人材が、DXやUX向上を推進してくれるため、安心して任せることができます。
まとめ
ここまで、DXとUXについてご紹介してきました。
とはいえ、どんな手法やフレームワークでも、ただそれを知っているだけではビジネスの結果には結びつきません。
結果として実らせるためには、実際に実践する中で経験を積み、手法を自分のものにしてゆく必要があります。
では、手堅く、リスクを最小限に実施するにはどうしたら良いのでしょう?
それは、「実績のある経験者のノウハウを参考にする」ことも一つの作戦だと思います。
ニジボックスは、リクルートの新規事業研究機関から誕生した経緯があり、UXデザインやデザイン思考をはじめとする様々なビジネス手法を実際にリクルートの新規事業でも数多く実施し、検証を重ねてきております。
DX推進をした事例もあるので、興味のある方はぜひこちらもお読みください。
下記資料では「ビジネスにUXが重要な理由」について、これまでニジボックスが培ってきた経験をもとに、事例を交えて分かりやすく解説しています。
UXへの理解を深めたい方、UXをビジネスに活かしていきたい方など、ご興味のある方はぜひお気軽に下記リンクより資料を無料ダウンロードください!

元ニジボックス 執行役員、TRTL Studio株式会社 CEO、その他顧問やエンジェル投資家として活動
コンサルティング会社でのUI開発経験を持つ技術者としてキャリアをスタート。リクルートホールディングス入社後、インキュベーション部門のUX組織と、グループ企業ニジボックスのデザイン部門を牽引。ニジボックスではPDMを経てデザインファーム事業を創設、事業部長に就任。その後執行役員として新しいUXソリューション開発を推進。2023年に退任。現在TRTL Venturesでインド投資・アジアのユニコーン企業の日本進出支援、その他新規事業・DX・UX・経営などの顧問や投資家として活動中。
X:@junmaruuuuu
note:junmaru228